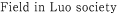жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖе…¬й–ӢгӮ·гғігғқгӮёгӮҰгғ
ж–ҮеҢ–иІЎгғ»дәәдҪ“гҒ®з•ҘеҘӘгҒЁиҝ”йӮ„вҖ•жӨҚж°‘ең°иІ¬д»»и«–гҒ®иҰ–зӮ№гҒӢгӮү
ж—ҘжҷӮпјҡ 2010е№ҙ12жңҲ12ж—ҘпјҲж—Ҙпјү10:00пҪһ18:00
е ҙжүҖпјҡ жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ 3йҡҺ еӨ§дјҡиӯ°е®Ө
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/about/access
е ұе‘Ҡ
в‘ гғ—гғӘгӮ·гғ©гғ»гғҮгғҙгӮ§гғғгғҲ(еҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҖҒгғӯгғјгӮәеӨ§еӯҰпјүгҖҢгӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®иҝ”йӮ„гҒЁеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…ҲдҪҸж°‘гҖҚ
в‘Ў жҹізҫҺйӮЈ (йҹ“еӣҪгҖҒеӣҪж°‘еӨ§еӯҰпјүгҖҢгҖҺж–ҮеҢ–иІЎдҝқеӯҳгҖҸгҒЁжӨҚж°‘ең°жё…з®—гҖҚ
в‘ў зңҹеҹҺзҷҫиҸҜпјҲжҙҘз”°еЎҫеӨ§еӯҰпјүгҖҢгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒәз”Јиҝ”йӮ„йҒӢеӢ•гҒ®еұ•й–ӢгҒЁгӮӘгғҷгғӘгӮ№гӮҜгҖҚгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖпјҲгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮд»®йЎҢпјү
еҸёдјҡпјҡ з¶Ідёӯжҳӯдё–пјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”/ж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲдјҡпјү
дҪҝз”ЁиЁҖиӘһпјҡж—Ҙжң¬иӘһпјӢиӢұиӘһпјҲдёҖйғЁйҖҡиЁігҒӮгӮҠпјү
еҸӮеҠ иІ»пјҡз„Ўж–ҷ
дё»еӮ¬пјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”еҹәе№№з ”з©¶гҖҢгӮўгғ•гғӘгӮ«ж–ҮеҢ–з ”з©¶гҒ«еҹәгҒҘгҒҸеӨҡе…ғзҡ„дё–з•ҢеғҸгҒ®жҺўжұӮгҖҚ
пјҸ科еӯҰз ”з©¶иІ»иЈңеҠ©йҮ‘гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҢи„ұжӨҚж°‘ең°еҢ–гҒ®еҸҢж–№еҗ‘зҡ„жӯҙеҸІйҒҺзЁӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҺжӨҚж°‘ең°иІ¬д»»гҖҸгҒ®з ”究гҖҚпјҲд»ЈиЎЁпјҡж°ёеҺҹйҷҪеӯҗпјү
е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳпјҡreparationws@gmail.com
пјңеҶ…е®№пјһ
2010е№ҙ8жңҲгҖҒгҖҢйҹ“еӣҪдҪөеҗҲ100е№ҙгҖҚгҒ«гҒ•гҒ„гҒ—гҒҰгҒ®гҖҒж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒӢгӮүйҹ“еӣҪгҒёгҒ®гҖҢжңқй®®зҺӢе®Өе„Җи»ҢгҖҚгҒ®гҖҢеј•гҒҚжёЎгҒ—гҖҚгҒҢи©ұйЎҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжӨҚж°‘ең°ж”Ҝй…ҚгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮӢж–ҮеҢ–иІЎгҒ®жөҒеҮәгҒЁгҒқгҒ®иҝ”йӮ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҖҒдё–з•ҢгҒ®еҗ„ең°гҒ§еӨ§гҒҚгҒӘиӯ°и«–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒӢгӮүгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҒӢгҒ°гӮҢгҖҒгҖҢ科еӯҰиӘҝжҹ»гҖҚгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒеҚҡзү©йӨЁгҒӘгҒ©гҒ«еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҹдәәйӘЁпјҲе ҙеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜз”ҹгҒҚгҒҹгҒҫгҒҫйҒӢгҒ°гӮҢгҒҹдәәгҖ…гҒЁгҒқгҒ®йҒәйӘЁпјүгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеЈ°гӮӮй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢж–ҮеҢ–иІЎгҖҚгҒЁгҖҢдәәдҪ“гҖҚгҒ®з•ҘеҘӘгҒҜйҮҚгҒӘгӮҠеҗҲгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гҒ®жӯҙеҸІгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
21дё–зҙҖгҒ®д»Ҡж—ҘгҖҒгҒӘгҒңгҖҒгҖҢж–ҮеҢ–иІЎгҖҚгӮ„гҖҢдәәйӘЁгҖҚгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢдәәгҖ…гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гҒЁи„ұжӨҚж°‘ең°еҢ–гҒ®жӯҙеҸІгҒЁгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖӮжң¬гӮ·гғігғқгӮёгӮҰгғ гҒ§гҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҖҢиҝ”йӮ„гҖҚгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹ3гҒӨгҒ®дәӢдҫӢгӮ’гҒЁгӮҠгҒӮгҒ’гҖҒгҖҢж–ҮеҢ–иІЎиҝ”йӮ„гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’гҖҒдё–з•ҢеҸІзҡ„гҒӘиҰ–йҮҺгҒӢгӮүиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–ҮеҢ–иІЎгғ»дәәдҪ“гҒ®з•ҘеҘӘгҒЁиҝ”йӮ„вҖ•жӨҚж°‘ең°иІ¬д»»и«–гҒ®иҰ–зӮ№гҒӢгӮү
ж—ҘжҷӮпјҡ 2010е№ҙ12жңҲ12ж—ҘпјҲж—Ҙпјү10:00пҪһ18:00
е ҙжүҖпјҡ жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ 3йҡҺ еӨ§дјҡиӯ°е®Ө
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/about/access
е ұе‘Ҡ
в‘ гғ—гғӘгӮ·гғ©гғ»гғҮгғҙгӮ§гғғгғҲ(еҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҖҒгғӯгғјгӮәеӨ§еӯҰпјүгҖҢгӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®иҝ”йӮ„гҒЁеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…ҲдҪҸж°‘гҖҚ
в‘Ў жҹізҫҺйӮЈ (йҹ“еӣҪгҖҒеӣҪж°‘еӨ§еӯҰпјүгҖҢгҖҺж–ҮеҢ–иІЎдҝқеӯҳгҖҸгҒЁжӨҚж°‘ең°жё…з®—гҖҚ
в‘ў зңҹеҹҺзҷҫиҸҜпјҲжҙҘз”°еЎҫеӨ§еӯҰпјүгҖҢгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒәз”Јиҝ”йӮ„йҒӢеӢ•гҒ®еұ•й–ӢгҒЁгӮӘгғҷгғӘгӮ№гӮҜгҖҚгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖпјҲгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮд»®йЎҢпјү
еҸёдјҡпјҡ з¶Ідёӯжҳӯдё–пјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”/ж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲдјҡпјү
дҪҝз”ЁиЁҖиӘһпјҡж—Ҙжң¬иӘһпјӢиӢұиӘһпјҲдёҖйғЁйҖҡиЁігҒӮгӮҠпјү
еҸӮеҠ иІ»пјҡз„Ўж–ҷ
дё»еӮ¬пјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”еҹәе№№з ”з©¶гҖҢгӮўгғ•гғӘгӮ«ж–ҮеҢ–з ”з©¶гҒ«еҹәгҒҘгҒҸеӨҡе…ғзҡ„дё–з•ҢеғҸгҒ®жҺўжұӮгҖҚ
пјҸ科еӯҰз ”з©¶иІ»иЈңеҠ©йҮ‘гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҢи„ұжӨҚж°‘ең°еҢ–гҒ®еҸҢж–№еҗ‘зҡ„жӯҙеҸІйҒҺзЁӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҺжӨҚж°‘ең°иІ¬д»»гҖҸгҒ®з ”究гҖҚпјҲд»ЈиЎЁпјҡж°ёеҺҹйҷҪеӯҗпјү
е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳпјҡreparationws@gmail.com
пјңеҶ…е®№пјһ
2010е№ҙ8жңҲгҖҒгҖҢйҹ“еӣҪдҪөеҗҲ100е№ҙгҖҚгҒ«гҒ•гҒ„гҒ—гҒҰгҒ®гҖҒж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒӢгӮүйҹ“еӣҪгҒёгҒ®гҖҢжңқй®®зҺӢе®Өе„Җи»ҢгҖҚгҒ®гҖҢеј•гҒҚжёЎгҒ—гҖҚгҒҢи©ұйЎҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжӨҚж°‘ең°ж”Ҝй…ҚгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮӢж–ҮеҢ–иІЎгҒ®жөҒеҮәгҒЁгҒқгҒ®иҝ”йӮ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҖҒдё–з•ҢгҒ®еҗ„ең°гҒ§еӨ§гҒҚгҒӘиӯ°и«–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒӢгӮүгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҒӢгҒ°гӮҢгҖҒгҖҢ科еӯҰиӘҝжҹ»гҖҚгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒеҚҡзү©йӨЁгҒӘгҒ©гҒ«еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҹдәәйӘЁпјҲе ҙеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜз”ҹгҒҚгҒҹгҒҫгҒҫйҒӢгҒ°гӮҢгҒҹдәәгҖ…гҒЁгҒқгҒ®йҒәйӘЁпјүгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеЈ°гӮӮй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢж–ҮеҢ–иІЎгҖҚгҒЁгҖҢдәәдҪ“гҖҚгҒ®з•ҘеҘӘгҒҜйҮҚгҒӘгӮҠеҗҲгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гҒ®жӯҙеҸІгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
21дё–зҙҖгҒ®д»Ҡж—ҘгҖҒгҒӘгҒңгҖҒгҖҢж–ҮеҢ–иІЎгҖҚгӮ„гҖҢдәәйӘЁгҖҚгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢдәәгҖ…гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гҒЁи„ұжӨҚж°‘ең°еҢ–гҒ®жӯҙеҸІгҒЁгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖӮжң¬гӮ·гғігғқгӮёгӮҰгғ гҒ§гҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҖҢиҝ”йӮ„гҖҚгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹ3гҒӨгҒ®дәӢдҫӢгӮ’гҒЁгӮҠгҒӮгҒ’гҖҒгҖҢж–ҮеҢ–иІЎиҝ”йӮ„гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’гҖҒдё–з•ҢеҸІзҡ„гҒӘиҰ–йҮҺгҒӢгӮүиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Posted by: shiino 2010/12/14 01:31:17
http://wwwsoc.nii.ac.jp/africa/j/activities/kanto.html#syukai
в—Ҷй–ўжқұж”ҜйғЁдё»еӮ¬пјҡпј’пјҗпј‘пјҗе№ҙеәҰгҖҖз ”з©¶йӣҶдјҡ
гҖҢгҖҺгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е№ҙгҖҸгҒӢгӮүеҚҠдё–зҙҖвҖ•йҒҺеҺ»гғ»зҸҫеңЁгғ»жңӘжқҘгҖҚ
гӮ»гғғгӮ·гғ§гғіпј’пјҡгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…¬е…ұгӮ’иҖғгҒҲгӮӢпјҲ13:00-15:00пјү
еҸёдјҡпјҡиҲ№з”°гӮҜгғ©гғјгӮ»гғігҒ•гӮ„гҒӢпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰпјү
第2гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®гҖҢе…¬е…ұпҪЈпјҲpublic-nessпјүгӮ’еӨҡи§’зҡ„гҒ«иӯ°и«–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд»Ҡж—ҘгҒ®гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ§йҮҚиҰҒгҒӘе•ҸйЎҢгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒҜгҖҒиӘ°гҒҢе…¬е…ұгӮ’жӢ…гҒҶгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮжң¬жқҘгҖҒе…¬е…ұгӮ’жӢ…гҒҶгҒҜгҒҡгҒ®еӣҪ家гҒҢгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж§ҳгҖ…гҒӘзҹӣзӣҫгӮ’еҶ…еҢ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒиҝ‘е№ҙеӨҡгҒҸгҒ®з ”究гҒҢжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒиӘ°гҒҢе…¬е…ұгӮ’жӢ…гҒҶгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮеёӮж°‘зӨҫдјҡгҒӢгҖҒе…ұеҗҢдҪ“гҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеӣҪйҡӣзӨҫдјҡгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮжң¬гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒЁиӘІйЎҢгӮ’гҖҒдёӢгҒӢгӮүжҚүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд»Ҡж—ҘгҖҒиіҮжәҗгҖҒз”ҹе‘ҪгҖҒжҖ§гҖҒеёӮж°‘жЁ©гҖҒ移民гҖҒе®—ж•ҷгҖҒиЁҖиӘһгҖҒж•ҷиӮІгҖҒзҙӣдәүгҒӘгҒ©гҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰеӨҡж§ҳгҒӘй ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе…¬е…ұгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҸӣиЁҖгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒиӘ°гҒҢдҪ•гӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘ°гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢж§ҳгҖ…гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҷҙеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжң¬гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…¬е…ұгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢе•ҸйЎҢй ҳеҹҹгҒ«еӨҡж§ҳгҒӘе•ҸйЎҢй ҳеҹҹгҒӢгӮүе…үгӮ’еҪ“гҒҰгҖҒгҒқгҒ®иӘІйЎҢгӮ„еҸҜиғҪжҖ§гӮ’и«–гҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгӮ№гғјгғҖгғіпјҚгҒӮгӮӢгӮўгғ•гғӘгӮ«еӣҪ家гҒ®з ҙ綻пјҹгҖҚгҖҖгҖҖгҖҖ
ж —з”°зҰҺеӯҗпјҲеҚғи‘үеӨ§еӯҰпјү
гҖҢгҖҺж°‘ж—ҸгҖҸгӮ’гҒ“гҒҲгҒҹе…¬е…ұжҖ§пјҚгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўиҫІжқ‘зӨҫдјҡгҒ®дәӢдҫӢгҒӢгӮүгҖҚгҖҖ
жқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺпјҲз«Ӣж•ҷеӨ§еӯҰпјү
гҖҢгӮұгғӢгӮўгғ»гғ«гӮӘжқ‘иҗҪзӨҫдјҡгҒ§е…¬е…ұжҖ§гӮ’иҖғгҒҲгӮӢпјҚзӢ¬з«ӢгҒӢгӮүгҖҺгӮұгғӢгӮўеҶҚз”ҹгҖҸгҒ®жңҹеҫ…гҒЁгҒ®гҒҜгҒ–гҒҫгҒ§гҖҚгҖҖгҖҖ
жӨҺйҮҺиӢҘиҸңпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰпјү
гӮігғЎгғігғҲпјҡеІ©дә•йӣӘд№ғпјҲж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰпјүгҖҒжӯҰеҶ…йҖІдёҖпјҲJICAз ”з©¶жүҖпјү
иіӘз–‘еҝңзӯ”
в—Ҷй–ўжқұж”ҜйғЁдё»еӮ¬пјҡпј’пјҗпј‘пјҗе№ҙеәҰгҖҖз ”з©¶йӣҶдјҡ
гҖҢгҖҺгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е№ҙгҖҸгҒӢгӮүеҚҠдё–зҙҖвҖ•йҒҺеҺ»гғ»зҸҫеңЁгғ»жңӘжқҘгҖҚ
гӮ»гғғгӮ·гғ§гғіпј’пјҡгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…¬е…ұгӮ’иҖғгҒҲгӮӢпјҲ13:00-15:00пјү
еҸёдјҡпјҡиҲ№з”°гӮҜгғ©гғјгӮ»гғігҒ•гӮ„гҒӢпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰпјү
第2гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®гҖҢе…¬е…ұпҪЈпјҲpublic-nessпјүгӮ’еӨҡи§’зҡ„гҒ«иӯ°и«–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд»Ҡж—ҘгҒ®гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ§йҮҚиҰҒгҒӘе•ҸйЎҢгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒҜгҖҒиӘ°гҒҢе…¬е…ұгӮ’жӢ…гҒҶгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮжң¬жқҘгҖҒе…¬е…ұгӮ’жӢ…гҒҶгҒҜгҒҡгҒ®еӣҪ家гҒҢгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж§ҳгҖ…гҒӘзҹӣзӣҫгӮ’еҶ…еҢ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒиҝ‘е№ҙеӨҡгҒҸгҒ®з ”究гҒҢжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒиӘ°гҒҢе…¬е…ұгӮ’жӢ…гҒҶгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮеёӮж°‘зӨҫдјҡгҒӢгҖҒе…ұеҗҢдҪ“гҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеӣҪйҡӣзӨҫдјҡгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮжң¬гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒЁиӘІйЎҢгӮ’гҖҒдёӢгҒӢгӮүжҚүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд»Ҡж—ҘгҖҒиіҮжәҗгҖҒз”ҹе‘ҪгҖҒжҖ§гҖҒеёӮж°‘жЁ©гҖҒ移民гҖҒе®—ж•ҷгҖҒиЁҖиӘһгҖҒж•ҷиӮІгҖҒзҙӣдәүгҒӘгҒ©гҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰеӨҡж§ҳгҒӘй ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе…¬е…ұгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҸӣиЁҖгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒиӘ°гҒҢдҪ•гӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘ°гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢж§ҳгҖ…гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҷҙеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжң¬гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…¬е…ұгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢе•ҸйЎҢй ҳеҹҹгҒ«еӨҡж§ҳгҒӘе•ҸйЎҢй ҳеҹҹгҒӢгӮүе…үгӮ’еҪ“гҒҰгҖҒгҒқгҒ®иӘІйЎҢгӮ„еҸҜиғҪжҖ§гӮ’и«–гҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгӮ№гғјгғҖгғіпјҚгҒӮгӮӢгӮўгғ•гғӘгӮ«еӣҪ家гҒ®з ҙ綻пјҹгҖҚгҖҖгҖҖгҖҖ
ж —з”°зҰҺеӯҗпјҲеҚғи‘үеӨ§еӯҰпјү
гҖҢгҖҺж°‘ж—ҸгҖҸгӮ’гҒ“гҒҲгҒҹе…¬е…ұжҖ§пјҚгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўиҫІжқ‘зӨҫдјҡгҒ®дәӢдҫӢгҒӢгӮүгҖҚгҖҖ
жқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺпјҲз«Ӣж•ҷеӨ§еӯҰпјү
гҖҢгӮұгғӢгӮўгғ»гғ«гӮӘжқ‘иҗҪзӨҫдјҡгҒ§е…¬е…ұжҖ§гӮ’иҖғгҒҲгӮӢпјҚзӢ¬з«ӢгҒӢгӮүгҖҺгӮұгғӢгӮўеҶҚз”ҹгҖҸгҒ®жңҹеҫ…гҒЁгҒ®гҒҜгҒ–гҒҫгҒ§гҖҚгҖҖгҖҖ
жӨҺйҮҺиӢҘиҸңпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰпјү
гӮігғЎгғігғҲпјҡеІ©дә•йӣӘд№ғпјҲж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰпјүгҖҒжӯҰеҶ…йҖІдёҖпјҲJICAз ”з©¶жүҖпјү
иіӘз–‘еҝңзӯ”
Posted by: shiino 2010/12/14 01:29:57
гғқгӮ№гӮҝгғјnull
жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”гӮўгғ•гғӘгӮ«ж–ҮеҢ–еҹәзӨҺз ”з©¶зҸӯе…¬й–ӢгӮ»гғҹгғҠгғј
The Return of Sara BaartmanгҖ”гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®её°йӮ„гҖ•пјҲеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«пјҢ2003е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ55еҲҶпјүдёҠжҳ дјҡ
ж—ҘжҷӮпјҡ2010е№ҙ12жңҲ7ж—ҘпјҲзҒ«пјү18:15пҪһ20:15
е ҙжүҖпјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ 3йҡҺ еӨ§дјҡиӯ°е®Ө
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/about/access
и§ЈиӘ¬пјҡж°ёеҺҹйҷҪеӯҗпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”пјү
еҸӮеҠ иІ»пјҡз„Ўж–ҷгҖҖ
дәӢеүҚз”іиҫјпјҡдёҚиҰҒпјҲгҒ©гҒӘгҒҹгҒ§гӮӮеҸӮеҠ гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷпјү
гҒҠе•ҸеҗҲгҒӣпјҡaaafrica@aa.tufs.ac.jp
д»ҠгҒӢгӮүгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©200е№ҙеүҚгҖҒеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒӢгӮүгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҖЈгӮҢгҒҰгҒ„гҒӢгӮҢгҖҒиҰӢдё–зү©гҒЁгҒ•гӮҢгҒҹе…ҲдҪҸж°‘еҘіжҖ§гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒҜгҖҒжӯ»еҫҢгҖҒи§Јеү–гҒ•гӮҢгҖҒи„ігҒЁеҘіжҖ§еҷЁгҒҢгғӣгғ«гғһгғӘгғіжј¬гҒ‘гҒ«гҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҖҒйӘЁж јжЁҷжң¬гғ»иқӢдәәеҪўгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§1970е№ҙд»ЈеҚҠгҒ°гҒҫгҒ§еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӮдҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®ж°‘дё»еҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮөгғ©гӮ’гҖҢдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж©ҹйҒӢгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҖҒ2002е№ҙгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№ж”ҝеәңгҒҢиҝ”йӮ„гҒ«еҗҲж„ҸгҒ—гҖҒгӮөгғ©гҒ®йҒәйӘёгҒҜж•…йғ·гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҖҒгҖҢжҲҰеҲ©е“ҒгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҢ科еӯҰзҡ„з ”з©¶гҖҚгҒ®жқҗж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гӮўгғ•гғӘгӮ«дәәгҒ®иә«дҪ“жЁҷжң¬гҒҢгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«жҢҒгҒЎеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҝ‘е№ҙгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеӢ•гҒҚгҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еҮәиҮӘгҒҢдёҚжҳҺгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮеӨҡгҒҸгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„иӘ°гҒ«гҖҢиҝ”йӮ„гҖҚгӮ’жұӮгӮҒгӮӢжЁ©еҲ©гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ©гҒ“гҒ«еҸ–гӮҠжҲ»гҒҷгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒӢгҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®иӯ°и«–гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиә«дҪ“жЁҷжң¬гҖҢиҝ”йӮ„гҖҚгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢе…ҲдҫӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®дәӢдҫӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгӮҫгғ©гғ»гғһгӮ»гӮігҒ«гӮҲгӮӢжҳ еғҸгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҝгҒӘгҒ•гҒҫгҒ®гҒ”еҸӮеҠ гӮ’гҒҠеҫ…гҒЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҠ10жңҲ25ж—ҘгҒ«еүҚз·ЁгӮ’дёҠжҳ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ”иҰ§гҒ«гҒӘгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж–№гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҫҢз·ЁгҒ®гҒҫгҒҲгҒ«дёҠжҳ гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
The Life and Times of Sara BaartmanгҖ”гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®з”ҹж¶ҜгҒЁжҷӮд»ЈгҖ•
пјҲеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«пјҢ1998е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ52еҲҶпјүдёҠжҳ дјҡ
ж—ҘжҷӮпјҡ2010е№ҙ12жңҲ7ж—ҘпјҲзҒ«пјү17:00пҪһ18:00
е ҙжүҖпјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ3йҡҺеӨ§дјҡиӯ°е®ӨпјҲ303пјү
д»ҠгҒӢгӮүгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©200е№ҙеүҚгҖҒеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…ҲдҪҸж°‘гӮігӮӨгӮігӮӨгҒ®еҘіжҖ§гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒҢгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҖЈгӮҢгҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒҜгҖҢгғӣгғғгғҶгғігғҲгғғгғҲгғ»гғҙгӮЈгғјгғҠгӮ№гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгғӯгғігғүгғігӮ„гғ‘гғӘгҒ®иҰӢдё–е°ҸеұӢгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒжӯ»еҫҢгҒҜи§Јеү–гҒ•гӮҢгҖҒи„ігҒЁеҘіжҖ§еҷЁгҒҢгғӣгғ«гғһгғӘгғіжј¬гҒ‘гҒ«гҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҖҒйӘЁж јжЁҷжң¬гғ»иқӢдәәеҪўгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§1970е№ҙд»ЈеҚҠгҒ°гҒҫгҒ§еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӮдҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®ж°‘дё»еҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮөгғ©гӮ’гҖҢдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж©ҹйҒӢгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҖҒ2002е№ҙгҒ«гӮөгғ©гҒҜгғ•гғ©гғігӮ№ж”ҝеәңгҒӢгӮүиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгҖҒж•…йғ·гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒ®её°йӮ„еҫҢгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘еҗ„ең°гҒ«гҒӮгӮӢгӮўгғ•гғӘгӮ«дәәгҒ®иә«дҪ“жЁҷжң¬гӮ„йҒәйӘЁгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеӢ•гҒҚгӮӮзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®жҳ з”»зӣЈзқЈгҖҒгӮҫгғ©гғ»гғһгӮ»гӮіпјҲZola MasekoпјүгҒ«гӮҲгӮӢжҳ еғҸгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«е…ҲдҪҸж°‘гҒ®жӯҙеҸІгҒЁжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гғ»дәәзЁ®дё»зҫ©гғ»гӮёгӮ§гғігғҖгғјгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”гӮўгғ•гғӘгӮ«ж–ҮеҢ–еҹәзӨҺз ”з©¶зҸӯе…¬й–ӢгӮ»гғҹгғҠгғј
The Return of Sara BaartmanгҖ”гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®её°йӮ„гҖ•пјҲеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«пјҢ2003е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ55еҲҶпјүдёҠжҳ дјҡ
ж—ҘжҷӮпјҡ2010е№ҙ12жңҲ7ж—ҘпјҲзҒ«пјү18:15пҪһ20:15
е ҙжүҖпјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ 3йҡҺ еӨ§дјҡиӯ°е®Ө
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/about/access
и§ЈиӘ¬пјҡж°ёеҺҹйҷҪеӯҗпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”пјү
еҸӮеҠ иІ»пјҡз„Ўж–ҷгҖҖ
дәӢеүҚз”іиҫјпјҡдёҚиҰҒпјҲгҒ©гҒӘгҒҹгҒ§гӮӮеҸӮеҠ гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷпјү
гҒҠе•ҸеҗҲгҒӣпјҡaaafrica@aa.tufs.ac.jp
д»ҠгҒӢгӮүгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©200е№ҙеүҚгҖҒеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒӢгӮүгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҖЈгӮҢгҒҰгҒ„гҒӢгӮҢгҖҒиҰӢдё–зү©гҒЁгҒ•гӮҢгҒҹе…ҲдҪҸж°‘еҘіжҖ§гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒҜгҖҒжӯ»еҫҢгҖҒи§Јеү–гҒ•гӮҢгҖҒи„ігҒЁеҘіжҖ§еҷЁгҒҢгғӣгғ«гғһгғӘгғіжј¬гҒ‘гҒ«гҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҖҒйӘЁж јжЁҷжң¬гғ»иқӢдәәеҪўгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§1970е№ҙд»ЈеҚҠгҒ°гҒҫгҒ§еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӮдҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®ж°‘дё»еҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮөгғ©гӮ’гҖҢдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж©ҹйҒӢгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҖҒ2002е№ҙгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№ж”ҝеәңгҒҢиҝ”йӮ„гҒ«еҗҲж„ҸгҒ—гҖҒгӮөгғ©гҒ®йҒәйӘёгҒҜж•…йғ·гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҖҒгҖҢжҲҰеҲ©е“ҒгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҢ科еӯҰзҡ„з ”з©¶гҖҚгҒ®жқҗж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гӮўгғ•гғӘгӮ«дәәгҒ®иә«дҪ“жЁҷжң¬гҒҢгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«жҢҒгҒЎеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҝ‘е№ҙгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеӢ•гҒҚгҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еҮәиҮӘгҒҢдёҚжҳҺгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮеӨҡгҒҸгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„иӘ°гҒ«гҖҢиҝ”йӮ„гҖҚгӮ’жұӮгӮҒгӮӢжЁ©еҲ©гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ©гҒ“гҒ«еҸ–гӮҠжҲ»гҒҷгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒӢгҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®иӯ°и«–гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиә«дҪ“жЁҷжң¬гҖҢиҝ”йӮ„гҖҚгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢе…ҲдҫӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®дәӢдҫӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгӮҫгғ©гғ»гғһгӮ»гӮігҒ«гӮҲгӮӢжҳ еғҸгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҝгҒӘгҒ•гҒҫгҒ®гҒ”еҸӮеҠ гӮ’гҒҠеҫ…гҒЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҠ10жңҲ25ж—ҘгҒ«еүҚз·ЁгӮ’дёҠжҳ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ”иҰ§гҒ«гҒӘгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж–№гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҫҢз·ЁгҒ®гҒҫгҒҲгҒ«дёҠжҳ гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
The Life and Times of Sara BaartmanгҖ”гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®з”ҹж¶ҜгҒЁжҷӮд»ЈгҖ•
пјҲеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«пјҢ1998е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ52еҲҶпјүдёҠжҳ дјҡ
ж—ҘжҷӮпјҡ2010е№ҙ12жңҲ7ж—ҘпјҲзҒ«пјү17:00пҪһ18:00
е ҙжүҖпјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ3йҡҺеӨ§дјҡиӯ°е®ӨпјҲ303пјү
д»ҠгҒӢгӮүгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©200е№ҙеүҚгҖҒеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…ҲдҪҸж°‘гӮігӮӨгӮігӮӨгҒ®еҘіжҖ§гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒҢгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҖЈгӮҢгҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒҜгҖҢгғӣгғғгғҶгғігғҲгғғгғҲгғ»гғҙгӮЈгғјгғҠгӮ№гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгғӯгғігғүгғігӮ„гғ‘гғӘгҒ®иҰӢдё–е°ҸеұӢгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒжӯ»еҫҢгҒҜи§Јеү–гҒ•гӮҢгҖҒи„ігҒЁеҘіжҖ§еҷЁгҒҢгғӣгғ«гғһгғӘгғіжј¬гҒ‘гҒ«гҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҖҒйӘЁж јжЁҷжң¬гғ»иқӢдәәеҪўгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§1970е№ҙд»ЈеҚҠгҒ°гҒҫгҒ§еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӮдҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®ж°‘дё»еҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮөгғ©гӮ’гҖҢдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж©ҹйҒӢгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҖҒ2002е№ҙгҒ«гӮөгғ©гҒҜгғ•гғ©гғігӮ№ж”ҝеәңгҒӢгӮүиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгҖҒж•…йғ·гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒ®её°йӮ„еҫҢгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘еҗ„ең°гҒ«гҒӮгӮӢгӮўгғ•гғӘгӮ«дәәгҒ®иә«дҪ“жЁҷжң¬гӮ„йҒәйӘЁгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеӢ•гҒҚгӮӮзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®жҳ з”»зӣЈзқЈгҖҒгӮҫгғ©гғ»гғһгӮ»гӮіпјҲZola MasekoпјүгҒ«гӮҲгӮӢжҳ еғҸгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«е…ҲдҪҸж°‘гҒ®жӯҙеҸІгҒЁжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гғ»дәәзЁ®дё»зҫ©гғ»гӮёгӮ§гғігғҖгғјгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
Posted by: shiino 2010/12/14 01:18:13
AAз ”е…ұеҗҢз ”з©¶гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲ
жӯҙеҸІзҡ„иҰізӮ№гҒӢгӮүиҰӢгҒҹгӮөгғҸгғ©д»ҘеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®иҫІжҘӯгҒЁж–ҮеҢ–пјҲд»ЈиЎЁпјҡзҹіе·қеҚҡжЁ№(AA з ”пјүпјү
12жңҲ4ж—ҘпјҲеңҹпјүе…¬й–Ӣз ”з©¶дјҡгҖҢгғҗгғҠгғҠпјҶеҒҪгғҗгғҠгғҠз ”з©¶дјҡгҖҚ
гҖҖ е ҙгҖҖжүҖгҖҖAA з ”гғһгғ«гғҒгғЎгғҮгӮЈгӮўдјҡиӯ°е®Ө(304)
гҖҖ жҷӮгҖҖй–“гҖҖ13:00 пҪһ 18:00
гҖҖ е ұе‘ҠиҖ…и—Өжң¬жӯҰ(дәәй–“з’°еўғеӨ§еӯҰ)гҖҒдҪҗи—Өйқ–жҳҺ(еӨ§йҳӘз”ЈжҘӯеӨ§еӯҰ)гҖҒзҹіе·қеҚҡжЁ№(AA з ”пјү
дјҡе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгғҗгғҠгғҠгҒҢгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»гҒҠгҒ„гҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»
жӯҙеҸІзҡ„иҰізӮ№гҒӢгӮүиҰӢгҒҹгӮөгғҸгғ©д»ҘеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®иҫІжҘӯгҒЁж–ҮеҢ–пјҲд»ЈиЎЁпјҡзҹіе·қеҚҡжЁ№(AA з ”пјүпјү
12жңҲ4ж—ҘпјҲеңҹпјүе…¬й–Ӣз ”з©¶дјҡгҖҢгғҗгғҠгғҠпјҶеҒҪгғҗгғҠгғҠз ”з©¶дјҡгҖҚ
гҖҖ е ҙгҖҖжүҖгҖҖAA з ”гғһгғ«гғҒгғЎгғҮгӮЈгӮўдјҡиӯ°е®Ө(304)
гҖҖ жҷӮгҖҖй–“гҖҖ13:00 пҪһ 18:00
гҖҖ е ұе‘ҠиҖ…и—Өжң¬жӯҰ(дәәй–“з’°еўғеӨ§еӯҰ)гҖҒдҪҗи—Өйқ–жҳҺ(еӨ§йҳӘз”ЈжҘӯеӨ§еӯҰ)гҖҒзҹіе·қеҚҡжЁ№(AA з ”пјү
дјҡе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгғҗгғҠгғҠгҒҢгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»гҒҠгҒ„гҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»
Posted by: shiino 2010/12/14 01:16:12
в—Ҹ第7еӣһFieldnetгғҜгғјгӮҜгӮ·гғ§гғғгғ—в—Ҹ
GPSгӮ’гҒӨгҒӢгҒЈгҒҰең°еӣігӮ’гҒӨгҒҸгӮҚгҒҶпјҒпҪһж–Үзі»гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®GPSи¶…еҲқеҝғиҖ…и¬ӣеә§гҖҖ第3еӣһ
http://bit.ly/gFazAM
ж—ҘжҷӮ пјҡ 2010е№ҙ12жңҲ4ж—ҘпјҲеңҹпјүгҖҖ11пјҡ00пҪһ13пјҡ30
е ҙжүҖ пјҡ жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖгҖҖ3йҡҺгҖҖе°Ҹдјҡиӯ°е®ӨпјҲ302пјү
гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ
1гҖҖпј§пј©пјігҒЁпј§пј°пјігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
2гҖҖжҙ»з”ЁдҫӢгҒ®зҙ№д»Ӣ
3гҖҖпј§пј°пјігғҮгғјгӮҝгҒ®еҸ–еҫ—пјҲйҮҺеӨ–пјү
4гҖҖпј§пј°пјігғҮгғјгӮҝгҒ®еҸ–гӮҠиҫјгҒҝгҒЁиЎЁзӨә
5гҖҖпј§пј©пјігӮ’гӮӮгҒЎгҒ„гҒҹеҲҶжһҗгҒ®е®ҹжј”
гҒҠз”ігҒ—иҫјгҒҝ
fieldnet[гҒӮгҒЈгҒЁ]tufs.ac.jpгҖҖпјҲгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҚгғғгғҲдәӢеӢҷеұҖпјү
гҒҠз”іиҫјгҒҝгҒҜгҖҒ12жңҲ2ж—ҘпјҲжңЁпјү17жҷӮгҒҫгҒ§гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҝ…иҰҒгҒӘж©ҹжқҗ
гғ»гӮ«гӮ·гғҹгғјгғ«3DпјҲгғ•гғӘгғјгӮҪгғ•гғҲпјүгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«жёҲгҒҝPC
гғ»GPSз«Ҝжң«пјҲGarminиЈҪгҒҢгғҷгӮҝгғјпјү
и¬ӣеё«гҒ®е®үеІЎгҒ•гӮ“гҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҒгҒҠгҒҸгҒ•гҒҫгҒ®гҒӢгҒҢгӮҠгҒ•гӮ“гӮӮгҖҒгҒ”еҚ”еҠӣгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҸӮеҠ иҖ…гҒ®гҒҝгҒӘгҒ•гҒҫгӮӮгҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹдёӯзҙҡз·ЁгҖҒгҒ„гӮүгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁжҷӮй–“гҒҢгҒ»гҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»
GPSгӮ’гҒӨгҒӢгҒЈгҒҰең°еӣігӮ’гҒӨгҒҸгӮҚгҒҶпјҒпҪһж–Үзі»гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®GPSи¶…еҲқеҝғиҖ…и¬ӣеә§гҖҖ第3еӣһ
http://bit.ly/gFazAM
ж—ҘжҷӮ пјҡ 2010е№ҙ12жңҲ4ж—ҘпјҲеңҹпјүгҖҖ11пјҡ00пҪһ13пјҡ30
е ҙжүҖ пјҡ жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖгҖҖ3йҡҺгҖҖе°Ҹдјҡиӯ°е®ӨпјҲ302пјү
гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ
1гҖҖпј§пј©пјігҒЁпј§пј°пјігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
2гҖҖжҙ»з”ЁдҫӢгҒ®зҙ№д»Ӣ
3гҖҖпј§пј°пјігғҮгғјгӮҝгҒ®еҸ–еҫ—пјҲйҮҺеӨ–пјү
4гҖҖпј§пј°пјігғҮгғјгӮҝгҒ®еҸ–гӮҠиҫјгҒҝгҒЁиЎЁзӨә
5гҖҖпј§пј©пјігӮ’гӮӮгҒЎгҒ„гҒҹеҲҶжһҗгҒ®е®ҹжј”
гҒҠз”ігҒ—иҫјгҒҝ
fieldnet[гҒӮгҒЈгҒЁ]tufs.ac.jpгҖҖпјҲгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҚгғғгғҲдәӢеӢҷеұҖпјү
гҒҠз”іиҫјгҒҝгҒҜгҖҒ12жңҲ2ж—ҘпјҲжңЁпјү17жҷӮгҒҫгҒ§гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҝ…иҰҒгҒӘж©ҹжқҗ
гғ»гӮ«гӮ·гғҹгғјгғ«3DпјҲгғ•гғӘгғјгӮҪгғ•гғҲпјүгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«жёҲгҒҝPC
гғ»GPSз«Ҝжң«пјҲGarminиЈҪгҒҢгғҷгӮҝгғјпјү
и¬ӣеё«гҒ®е®үеІЎгҒ•гӮ“гҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҒгҒҠгҒҸгҒ•гҒҫгҒ®гҒӢгҒҢгӮҠгҒ•гӮ“гӮӮгҖҒгҒ”еҚ”еҠӣгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҸӮеҠ иҖ…гҒ®гҒҝгҒӘгҒ•гҒҫгӮӮгҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹдёӯзҙҡз·ЁгҖҒгҒ„гӮүгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁжҷӮй–“гҒҢгҒ»гҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»
Posted by: shiino 2010/12/14 01:11:12
 2010е№ҙ12жңҲ2ж—ҘзҚЁеҚ”еӨ§еӯҰгҖҢе…ЁеӯҰз·ҸеҗҲи¬ӣеә§гғ»гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒ§иӘӯгҒҝи§ЈгҒҸдё–з•ҢгҖҚ
2010е№ҙ12жңҲ2ж—ҘзҚЁеҚ”еӨ§еӯҰгҖҢе…ЁеӯҰз·ҸеҗҲи¬ӣеә§гғ»гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒ§иӘӯгҒҝи§ЈгҒҸдё–з•ҢгҖҚзҚЁеҚ”еӨ§еӯҰ
гҖҢе…ЁеӯҰз·ҸеҗҲи¬ӣеә§гғ»гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒ§иӘӯгҒҝи§ЈгҒҸдё–з•ҢгҖҚ
гӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјпјҡй Ҳж°ёе’ҢеҚҡе…Ҳз”ҹ
гҖҢ家ж—ҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰ гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒҷгӮӢпјҡжқұгӮўгғ•гғӘгӮ«гҖҒгӮұгғӢгӮўгғ»гғ«гӮӘжқ‘иҗҪгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиӘҝжҹ»гҒӢгӮүгҖҚ
жӨҺйҮҺиӢҘиҸң
вҳ…йҖЈж—ҘгҖҒгҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰд»–еӨ§еӯҰгҒёгҖӮзӢ¬еҚ”еӨ§еӯҰгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§й©ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж„ҹжғігӮӮжІўеұұжӣёгҒ„гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҖҒеӯҰз”ҹгҒ•гӮ“гҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҖӮ
гҖҢе…ЁеӯҰз·ҸеҗҲи¬ӣеә§гғ»гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒ§иӘӯгҒҝи§ЈгҒҸдё–з•ҢгҖҚ
гӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјпјҡй Ҳж°ёе’ҢеҚҡе…Ҳз”ҹ
гҖҢ家ж—ҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰ гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒҷгӮӢпјҡжқұгӮўгғ•гғӘгӮ«гҖҒгӮұгғӢгӮўгғ»гғ«гӮӘжқ‘иҗҪгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиӘҝжҹ»гҒӢгӮүгҖҚ
жӨҺйҮҺиӢҘиҸң
вҳ…йҖЈж—ҘгҖҒгҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰд»–еӨ§еӯҰгҒёгҖӮзӢ¬еҚ”еӨ§еӯҰгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§й©ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж„ҹжғігӮӮжІўеұұжӣёгҒ„гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҖҒеӯҰз”ҹгҒ•гӮ“гҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҖӮ
Posted by: shiino 2010/12/14 01:06:54
гҖҗи¬ӣжј”ж—ҘгҖ‘2010е№ҙ12жңҲ1ж—Ҙ
гҖҗи¬ӣжј”иҖ…еҗҚгҖ‘жӨҺйҮҺиӢҘиҸң Wakana SHIINO
гҖҗгӮ«гғҶгӮҙгғӘгҖ‘зӨҫдјҡдәәйЎһеӯҰ
жқұгӮўгғ•гғӘгӮ«гҖҒ гӮұгғӢгӮўжқ‘иҗҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖҖ家ж—ҸгҒЁжҡ®гӮүгҒҷпјҡдәәйЎһеӯҰгҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒЁз ”究
гҖҗгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҖ‘жқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдёҖиІ«гҒ—гҒҰгӮұгғӢгӮўгғ»гғ«гӮӘзӨҫдјҡгҒ®ж°‘ж—ҸиӘҢзҡ„з ”з©¶гӮ’йҮҚгҒӯгҖҒ2004е№ҙгҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гӮўгғ•гғӘгӮ«еӯҰдјҡ第16еӣһз ”з©¶еҘЁеҠұиіһгӮ’еҸ—иіһгҖӮжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖFSC(гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгӮөгӮӨгӮЁгғігӮ№з ”究дјҒз”»гӮ»гғігӮҝгғј)жүҖеұһгҖӮйҖҡж–ҮеҢ–зҡ„з ”з©¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚз ”з©¶гӮ’иЎҢгҒҶеӮҚгӮүгҖҒеӯҰйҡӣзҡ„гҒ«гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮ«гғјгӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜFieldnetгӮ’дјҒз”»йҒӢе–¶гҖӮж•ҷиӮІйқўгҒ§гҒҜгҒҠиҢ¶гҒ®ж°ҙеҘіеӯҗеӨ§еӯҰзӯүгҒ§ж•ҷйһӯгӮ’гҒЁгӮӢгҖӮ
гҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸңгҖҖгӮөгӮӨгғҲ: http://wakana-luo.aacore.jp/
гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҚгғғгғҲгҒ®гӮөгӮӨгғҲпјҡhttp://fieldnet.aacore.jp
гҒ”жқҘе ҙгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹгҒҝгҒӘгҒ•гҒҫгҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҒпјҒ
гҒ„гҒ„йӣ°еӣІж°—гҒ®еӨ§еӯҰгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҗи¬ӣжј”иҖ…еҗҚгҖ‘жӨҺйҮҺиӢҘиҸң Wakana SHIINO
гҖҗгӮ«гғҶгӮҙгғӘгҖ‘зӨҫдјҡдәәйЎһеӯҰ
жқұгӮўгғ•гғӘгӮ«гҖҒ гӮұгғӢгӮўжқ‘иҗҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖҖ家ж—ҸгҒЁжҡ®гӮүгҒҷпјҡдәәйЎһеӯҰгҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒЁз ”究
гҖҗгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҖ‘жқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдёҖиІ«гҒ—гҒҰгӮұгғӢгӮўгғ»гғ«гӮӘзӨҫдјҡгҒ®ж°‘ж—ҸиӘҢзҡ„з ”з©¶гӮ’йҮҚгҒӯгҖҒ2004е№ҙгҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гӮўгғ•гғӘгӮ«еӯҰдјҡ第16еӣһз ”з©¶еҘЁеҠұиіһгӮ’еҸ—иіһгҖӮжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖFSC(гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгӮөгӮӨгӮЁгғігӮ№з ”究дјҒз”»гӮ»гғігӮҝгғј)жүҖеұһгҖӮйҖҡж–ҮеҢ–зҡ„з ”з©¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚз ”з©¶гӮ’иЎҢгҒҶеӮҚгӮүгҖҒеӯҰйҡӣзҡ„гҒ«гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮ«гғјгӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜFieldnetгӮ’дјҒз”»йҒӢе–¶гҖӮж•ҷиӮІйқўгҒ§гҒҜгҒҠиҢ¶гҒ®ж°ҙеҘіеӯҗеӨ§еӯҰзӯүгҒ§ж•ҷйһӯгӮ’гҒЁгӮӢгҖӮ
гҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸңгҖҖгӮөгӮӨгғҲ: http://wakana-luo.aacore.jp/
гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҚгғғгғҲгҒ®гӮөгӮӨгғҲпјҡhttp://fieldnet.aacore.jp
гҒ”жқҘе ҙгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹгҒҝгҒӘгҒ•гҒҫгҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҒпјҒ
гҒ„гҒ„йӣ°еӣІж°—гҒ®еӨ§еӯҰгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
Posted by: shiino 2010/12/14 01:01:54
жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜй–ўиҘҝгҖҒдёӯеӣҪеӣӣеӣҪгҖҒеұұйҷ°гҖҒзҹіе·қгҖҒзҰҸдә•зңҢпјҲ16еәңзңҢпјүгҖҒ200ж•°еҚҒдёҮйғЁгҖӮ
еӨ§йҳӘгҒ•гҒӢгӮүеҸ–жқҗгҒ«гҒҚгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹжңЁе…ғиЁҳиҖ…гҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

amazon гҒӢгӮүгҒ©гҒҶгҒһ
пјңзӣ®ж¬Ўпјһ
гҖҺгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгҒ§з”ҹгҒҚгӮӢвҖ•вҖ•дәәйЎһеӯҰиҖ…гҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒӢгӮүгҖҸгҖҖзӣ®ж¬Ў
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гғјгғјгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгҒ§з”ҹгҒҚгӮӢгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸң
з¬¬пј‘з« гҖҖдәәйЎһеӯҰиҖ…гҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒӢгӮү
ж—ўе©ҡгҒЁгӮ·гғігӮ°гғ«гҒ®гҖҢеўғз•ҢгҖҚгӮ’иЎҢгҒҚжқҘгҒҷгӮӢеҘігҒҹгҒЎгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҲҗжҫӨеҫіеӯҗгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖвҖ•вҖ•гҖҖгӮ¶гғігғ“гӮўгғ»гғҲгғігӮ¬зӨҫдјҡ
гғӢгғҘгғјгӮ®гғӢгӮўгҒ®гҖҢгӮӮгҒҰгҒӘгҒ„з”·гҖҚгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖз”°жүҖиҒ–еҝ—
гӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғ’гӮёгғҘгғ©гҒЁз§ҒгҒЁгҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜ
гҖҢзӢ¬гӮҠгҖҚгҒ®з§ҒгҒӢгӮүгҖҒгҖҢдәҢйҮҚгҖҚгҒ®з§ҒгӮ’ж„ҹеҫ—гҒҷгӮӢгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеңӢејҳжҡҒеӯҗ
з¬¬пј’з« гҖҖгӮ·гғігӮ°гғ«гҒӢгӮүиҰӢгҒҲгӮӢзӨҫдјҡ
гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ¬гҖҚгҒҹгҒЎгҒ®гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®йЎ”гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе®Үз”°е·қеҰҷеӯҗ
гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгӮ’гҒІгӮүгҒҸвҖ•вҖ•гғ•гғ©гғігӮ№гғ»гғ‘гғӘең°еҹҹгҒ®гҒІгҒЁгӮҠГ—гҒІгҒЁгҒігҒЁгҖҖжӨҚжқ‘жё…еҠ
гҒІгҒЁгӮҠгҒ§жҡ®гӮүгҒ—гҖҒгҒІгҒЁгӮҠгҒ§иҖҒгҒ„гӮӢгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖй«ҳж©ӢзөөйҮҢйҰҷ
вҖ•вҖ•еҢ—欧еһӢзҰҸзҘүеӣҪ家гҒ®ж”ҜгҒҲгӮӢгҖҢеҖӢдәәгҖҚзҡ„з”ҹжҙ»гҖҖ
гҖҢгӮӘгғўгғӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҫгӮҰгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒгӮөгӮӨгҒ®и§’гҒ«гҒЁгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁ
вҖ•вҖ•йҹ“еӣҪгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гҒ®дёҚзўәгҒӢгҒ•гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеІЎз”°жө©жЁ№
еҜЎе©ҰвҖ•вҖ•йғҪеҗҲгҒ®гҒ„гҒ„еҘіпјҹгҒқгӮҢгҒЁгӮӮжӮӘгҒ„еҘіпјҹгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖз”°дёӯйӣ…дёҖ
з¬¬пј“з« гҖҖеҲҘгӮҢгҒ®йўЁжҷҜ
гӮ·гғігӮ°гғ«гҒ гҒЈгҒҰгҒёгҒЈгҒЎгӮғгӮүгӮҲпјҒпјҹгҖҖвҖ•вҖ•гғ‘гғ—гӮўгғӢгғҘгғјгӮ®гғӢгӮўгғ»гғһгғҢгӮ№еі¶гҒ®
гӮ·гғігӮ°гғ«гғһгӮ¶гғјгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖйҰ¬е ҙгҖҖж·і
йқһе©ҡгҒ®йҒёжҠһвҖ•гғқгғӘгғҚгӮ·гӮўгҒ®гӮҜгғғгӮҜи«ёеі¶гғһгӮӘгғӘжөҒ гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ гҖҖжЈҡж©ӢгҖҖиЁ“
гӮігғўгғӯгҒ®дёүгҒҸгҒ гӮҠеҚҠдәӢжғ…гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖиҠұжё•гҖҖйҰЁд№ҹ
гҖҖ
з¬¬пј”з« гҖҖй—Ҡжӯ©гҒҷгӮӢгӮ·гғігӮ°гғ«еҘіжҖ§гҒҹгҒЎ
гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгҒЁеҗҚд№—гӮҠе§ӢгӮҒгҒҹеҘіжҖ§гҒҹгҒЎ
вҖ•вҖ•гғҚгғ‘гғјгғ«зүҲгӮ·гғігӮ°гғ«дәӢжғ…гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе№…еҙҺйә»зҙҖеӯҗ
гҖҢе……гҒЎи¶ігӮҠгҒҹеҘігҖҚгҒ®еҮәзҸҫпјҹвҖ•вҖ•зҸҫд»Јж—Ҙжң¬гҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«еҘіжҖ§ гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеҰҷжңЁеҝҚ
гӮ·гғігӮ°гғ«гӮ’гҒҜгҒҳгҒҚгҒ гҒҷжқ‘гҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«гҒ®йғҪгғ»гғҠгӮӨгғӯгғ“гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸң
гғўгғ«гӮ®гғјгҒ•гӮ“гҒ®еҶ’йҷәвҖ•еҢ—гӮӨгғігғүиҫІжқ‘гҒ®зү©иӘһгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе…«жңЁзҘҗеӯҗ
гҒҠгӮҸгӮҠгҒ«гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸң
гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгҖҒд»ҠжҖқгҒҶгҒ“гҒЁпјҲгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҒЁе…ұгҒ«пјүеҹ·зӯҶиҖ…дёҖеҗҢ
еӨ§йҳӘгҒ•гҒӢгӮүеҸ–жқҗгҒ«гҒҚгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹжңЁе…ғиЁҳиҖ…гҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

amazon гҒӢгӮүгҒ©гҒҶгҒһ
пјңзӣ®ж¬Ўпјһ
гҖҺгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгҒ§з”ҹгҒҚгӮӢвҖ•вҖ•дәәйЎһеӯҰиҖ…гҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒӢгӮүгҖҸгҖҖзӣ®ж¬Ў
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гғјгғјгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгҒ§з”ҹгҒҚгӮӢгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸң
з¬¬пј‘з« гҖҖдәәйЎһеӯҰиҖ…гҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒӢгӮү
ж—ўе©ҡгҒЁгӮ·гғігӮ°гғ«гҒ®гҖҢеўғз•ҢгҖҚгӮ’иЎҢгҒҚжқҘгҒҷгӮӢеҘігҒҹгҒЎгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҲҗжҫӨеҫіеӯҗгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖвҖ•вҖ•гҖҖгӮ¶гғігғ“гӮўгғ»гғҲгғігӮ¬зӨҫдјҡ
гғӢгғҘгғјгӮ®гғӢгӮўгҒ®гҖҢгӮӮгҒҰгҒӘгҒ„з”·гҖҚгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖз”°жүҖиҒ–еҝ—
гӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғ’гӮёгғҘгғ©гҒЁз§ҒгҒЁгҒ®гғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜ
гҖҢзӢ¬гӮҠгҖҚгҒ®з§ҒгҒӢгӮүгҖҒгҖҢдәҢйҮҚгҖҚгҒ®з§ҒгӮ’ж„ҹеҫ—гҒҷгӮӢгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеңӢејҳжҡҒеӯҗ
з¬¬пј’з« гҖҖгӮ·гғігӮ°гғ«гҒӢгӮүиҰӢгҒҲгӮӢзӨҫдјҡ
гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ¬гҖҚгҒҹгҒЎгҒ®гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®йЎ”гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе®Үз”°е·қеҰҷеӯҗ
гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгӮ’гҒІгӮүгҒҸвҖ•вҖ•гғ•гғ©гғігӮ№гғ»гғ‘гғӘең°еҹҹгҒ®гҒІгҒЁгӮҠГ—гҒІгҒЁгҒігҒЁгҖҖжӨҚжқ‘жё…еҠ
гҒІгҒЁгӮҠгҒ§жҡ®гӮүгҒ—гҖҒгҒІгҒЁгӮҠгҒ§иҖҒгҒ„гӮӢгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖй«ҳж©ӢзөөйҮҢйҰҷ
вҖ•вҖ•еҢ—欧еһӢзҰҸзҘүеӣҪ家гҒ®ж”ҜгҒҲгӮӢгҖҢеҖӢдәәгҖҚзҡ„з”ҹжҙ»гҖҖ
гҖҢгӮӘгғўгғӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҫгӮҰгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒгӮөгӮӨгҒ®и§’гҒ«гҒЁгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁ
вҖ•вҖ•йҹ“еӣҪгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гҒ®дёҚзўәгҒӢгҒ•гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеІЎз”°жө©жЁ№
еҜЎе©ҰвҖ•вҖ•йғҪеҗҲгҒ®гҒ„гҒ„еҘіпјҹгҒқгӮҢгҒЁгӮӮжӮӘгҒ„еҘіпјҹгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖз”°дёӯйӣ…дёҖ
з¬¬пј“з« гҖҖеҲҘгӮҢгҒ®йўЁжҷҜ
гӮ·гғігӮ°гғ«гҒ гҒЈгҒҰгҒёгҒЈгҒЎгӮғгӮүгӮҲпјҒпјҹгҖҖвҖ•вҖ•гғ‘гғ—гӮўгғӢгғҘгғјгӮ®гғӢгӮўгғ»гғһгғҢгӮ№еі¶гҒ®
гӮ·гғігӮ°гғ«гғһгӮ¶гғјгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖйҰ¬е ҙгҖҖж·і
йқһе©ҡгҒ®йҒёжҠһвҖ•гғқгғӘгғҚгӮ·гӮўгҒ®гӮҜгғғгӮҜи«ёеі¶гғһгӮӘгғӘжөҒ гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ гҖҖжЈҡж©ӢгҖҖиЁ“
гӮігғўгғӯгҒ®дёүгҒҸгҒ гӮҠеҚҠдәӢжғ…гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖиҠұжё•гҖҖйҰЁд№ҹ
гҖҖ
з¬¬пј”з« гҖҖй—Ҡжӯ©гҒҷгӮӢгӮ·гғігӮ°гғ«еҘіжҖ§гҒҹгҒЎ
гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгҒЁеҗҚд№—гӮҠе§ӢгӮҒгҒҹеҘіжҖ§гҒҹгҒЎ
вҖ•вҖ•гғҚгғ‘гғјгғ«зүҲгӮ·гғігӮ°гғ«дәӢжғ…гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе№…еҙҺйә»зҙҖеӯҗ
гҖҢе……гҒЎи¶ігӮҠгҒҹеҘігҖҚгҒ®еҮәзҸҫпјҹвҖ•вҖ•зҸҫд»Јж—Ҙжң¬гҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«еҘіжҖ§ гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеҰҷжңЁеҝҚ
гӮ·гғігӮ°гғ«гӮ’гҒҜгҒҳгҒҚгҒ гҒҷжқ‘гҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«гҒ®йғҪгғ»гғҠгӮӨгғӯгғ“гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸң
гғўгғ«гӮ®гғјгҒ•гӮ“гҒ®еҶ’йҷәвҖ•еҢ—гӮӨгғігғүиҫІжқ‘гҒ®зү©иӘһгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе…«жңЁзҘҗеӯҗ
гҒҠгӮҸгӮҠгҒ«гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸң
гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гҖҚгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгҖҒд»ҠжҖқгҒҶгҒ“гҒЁпјҲгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҒЁе…ұгҒ«пјүеҹ·зӯҶиҖ…дёҖеҗҢ
Posted by: shiino 2010/12/14 00:31:13
вҳ…жқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰAAз ”гӮўгғ•гғӘгӮ«ж–ҮеҢ–еҹәзӨҺз ”з©¶зҸӯе…¬й–ӢгӮ»гғҹгғҠгғјвҳ…
The Life and Times of Sara BaartmanгҖ”гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®з”ҹж¶ҜгҒЁжҷӮд»ЈгҖ•
пјҲеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«пјҢ1998е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ52еҲҶпјүдёҠжҳ дјҡ
ж—ҘжҷӮпјҡ2010е№ҙ10жңҲ25ж—ҘпјҲжңҲпјү18:15пҪһ20:15
е ҙжүҖпјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ3йҡҺеӨ§дјҡиӯ°е®ӨпјҲ303пјү
и§ЈиӘ¬пјҡж°ёеҺҹйҷҪеӯҗпјҲAAз ”пјҸеҚ—йғЁгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®жӯҙеҸІпјү
еҸӮеҠ иІ»пјҡз„Ўж–ҷгҖҖ
дәӢеүҚз”іиҫјпјҡдёҚиҰҒпјҲгҒ©гҒӘгҒҹгҒ§гӮӮеҸӮеҠ гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷпјү
гҒҠе•ҸеҗҲгҒӣпјҡaaafrica@aa.tufs.ac.jp
д»ҠгҒӢгӮүгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©200е№ҙеүҚгҖҒеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…ҲдҪҸж°‘гӮігӮӨгӮігӮӨгҒ®еҘіжҖ§гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒҢгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҖЈгӮҢгҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒҜгҖҢгғӣгғғгғҶгғігғҲгғғгғҲгғ»гғҙгӮЈгғјгғҠгӮ№гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгғӯгғігғүгғігӮ„гғ‘гғӘгҒ®иҰӢдё–е°ҸеұӢгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒжӯ»еҫҢгҒҜи§Јеү–гҒ•гӮҢгҖҒи„ігҒЁеҘіжҖ§еҷЁгҒҢгғӣгғ«гғһгғӘгғіжј¬гҒ‘гҒ«гҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҖҒйӘЁж јжЁҷжң¬гғ»иқӢдәәеҪўгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§1970е№ҙд»ЈеҚҠгҒ°гҒҫгҒ§еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӮдҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®ж°‘дё»еҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮөгғ©гӮ’гҖҢдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж©ҹйҒӢгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҖҒ2002е№ҙгҒ«гӮөгғ©гҒҜгғ•гғ©гғігӮ№ж”ҝеәңгҒӢгӮүиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгҖҒж•…йғ·гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒ®её°йӮ„еҫҢгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘еҗ„ең°гҒ«гҒӮгӮӢгӮўгғ•гғӘгӮ«дәәгҒ®иә«дҪ“жЁҷжң¬гӮ„йҒәйӘЁгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеӢ•гҒҚгӮӮзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®жҳ з”»зӣЈзқЈгҖҒгӮҫгғ©гғ»гғһгӮ»гӮіпјҲZola MasekoпјүгҒ«гӮҲгӮӢжҳ еғҸгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«е…ҲдҪҸж°‘гҒ®жӯҙеҸІгҒЁжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гғ»дәәзЁ®дё»зҫ©гғ»гӮёгӮ§гғігғҖгғјгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒжң¬дҪңгҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғ©гҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеЈ°гҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжҷӮжңҹгҒҫгҒ§гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒёгҒ®иҝ”йӮ„гҒҫгҒ§гӮ’жүұгҒЈгҒҹз¶ҡз·ЁгҖҢThe Return of Sara BaartmanгҖҚгҖ” гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®её°йӮ„гҖ•пјҲZola MasekoиЈҪдҪңпјҢ2003е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ55еҲҶпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ12жңҲ7ж—ҘпјҲзҒ«пјүгҒ«дёҠжҳ гӮ’дәҲе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгҒ®гҒ”еҸӮеҠ гӮ’гҒҠеҫ…гҒЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
вҳ…гҒҠеҝҷгҒ—гҒ„дёӯгҖҒгҒ”еҸӮеҠ гҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҒпјҒпјҒгҒ„гҒ„иӯ°и«–гӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж¬ЎеӣһгҒҜ12жңҲ7ж—ҘгҒ®еӨңгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒй–Ӣе§ӢгҒҫгҒҲгҒ«еүҚз·ЁгӮ’гҒҝгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж–№гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дёҠжҳ гӮ’дәҲе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
The Life and Times of Sara BaartmanгҖ”гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®з”ҹж¶ҜгҒЁжҷӮд»ЈгҖ•
пјҲеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«пјҢ1998е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ52еҲҶпјүдёҠжҳ дјҡ
ж—ҘжҷӮпјҡ2010е№ҙ10жңҲ25ж—ҘпјҲжңҲпјү18:15пҪһ20:15
е ҙжүҖпјҡжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖ3йҡҺеӨ§дјҡиӯ°е®ӨпјҲ303пјү
и§ЈиӘ¬пјҡж°ёеҺҹйҷҪеӯҗпјҲAAз ”пјҸеҚ—йғЁгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®жӯҙеҸІпјү
еҸӮеҠ иІ»пјҡз„Ўж–ҷгҖҖ
дәӢеүҚз”іиҫјпјҡдёҚиҰҒпјҲгҒ©гҒӘгҒҹгҒ§гӮӮеҸӮеҠ гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷпјү
гҒҠе•ҸеҗҲгҒӣпјҡaaafrica@aa.tufs.ac.jp
д»ҠгҒӢгӮүгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©200е№ҙеүҚгҖҒеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е…ҲдҪҸж°‘гӮігӮӨгӮігӮӨгҒ®еҘіжҖ§гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒҢгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«йҖЈгӮҢгҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒҜгҖҢгғӣгғғгғҶгғігғҲгғғгғҲгғ»гғҙгӮЈгғјгғҠгӮ№гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгғӯгғігғүгғігӮ„гғ‘гғӘгҒ®иҰӢдё–е°ҸеұӢгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒжӯ»еҫҢгҒҜи§Јеү–гҒ•гӮҢгҖҒи„ігҒЁеҘіжҖ§еҷЁгҒҢгғӣгғ«гғһгғӘгғіжј¬гҒ‘гҒ«гҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҖҒйӘЁж јжЁҷжң¬гғ»иқӢдәәеҪўгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ§1970е№ҙд»ЈеҚҠгҒ°гҒҫгҒ§еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӮдҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®ж°‘дё»еҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮөгғ©гӮ’гҖҢдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠжҲ»гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж©ҹйҒӢгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҖҒ2002е№ҙгҒ«гӮөгғ©гҒҜгғ•гғ©гғігӮ№ж”ҝеәңгҒӢгӮүиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгҖҒж•…йғ·гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғ©гҒ®её°йӮ„еҫҢгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘еҗ„ең°гҒ«гҒӮгӮӢгӮўгғ•гғӘгӮ«дәәгҒ®иә«дҪ“жЁҷжң¬гӮ„йҒәйӘЁгҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеӢ•гҒҚгӮӮзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®жҳ з”»зӣЈзқЈгҖҒгӮҫгғ©гғ»гғһгӮ»гӮіпјҲZola MasekoпјүгҒ«гӮҲгӮӢжҳ еғҸгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«е…ҲдҪҸж°‘гҒ®жӯҙеҸІгҒЁжӨҚж°‘ең°дё»зҫ©гғ»дәәзЁ®дё»зҫ©гғ»гӮёгӮ§гғігғҖгғјгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒжң¬дҪңгҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғ©гҒ®иҝ”йӮ„гӮ’жұӮгӮҒгӮӢеЈ°гҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжҷӮжңҹгҒҫгҒ§гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒёгҒ®иҝ”йӮ„гҒҫгҒ§гӮ’жүұгҒЈгҒҹз¶ҡз·ЁгҖҢThe Return of Sara BaartmanгҖҚгҖ” гӮөгғ©гғ»гғҗгғјгғ«гғҲгғһгғігҒ®её°йӮ„гҖ•пјҲZola MasekoиЈҪдҪңпјҢ2003е№ҙпјҢиӢұиӘһпјҢ55еҲҶпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ12жңҲ7ж—ҘпјҲзҒ«пјүгҒ«дёҠжҳ гӮ’дәҲе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгҒ®гҒ”еҸӮеҠ гӮ’гҒҠеҫ…гҒЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
вҳ…гҒҠеҝҷгҒ—гҒ„дёӯгҖҒгҒ”еҸӮеҠ гҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҒпјҒпјҒгҒ„гҒ„иӯ°и«–гӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж¬ЎеӣһгҒҜ12жңҲ7ж—ҘгҒ®еӨңгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒй–Ӣе§ӢгҒҫгҒҲгҒ«еүҚз·ЁгӮ’гҒҝгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж–№гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дёҠжҳ гӮ’дәҲе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Posted by: shiino 2010/10/24 03:07:57
11жңҲ6ж—ҘгҒ«з«Ӣж•ҷеӨ§гҒ§й–ӢеӮ¬пјҒпјҒ
гғ•гғ©гӮӨгғӨгғјгҒҜгҒ“гҒЎгӮүвҶ“
null
2010гҖҒ2011е№ҙеәҰгҒЁж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰдјҡгҒ®й–ўжқұең°еҢәжҮҮи«ҮдјҡгҒ®е№№дәӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәәйҒёгҒ—гҒҰгҖҒзҹіз”°ж…ҺдёҖйғҺгҖҒеӯ«жҡҒеүӣгҖҒй«ҳйҮҺгҒ•гӮ„гҒӢгҖҒжқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺгҖҒжёЎйӮүжҡҒеӯҗгҒ•гӮ“гӮүгӮ’гҒІгҒҚгҒ“гҒҝгҖҒ
дјҡеҗҲгӮ’гҒІгӮүгҒҚгҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢиӯ°и«–гҒ—гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдјҒз”»гӮ’гҒӢгӮ“гҒҢгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2010е№ҙеәҰпҪһгҖҖж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰдјҡй–ўжқұең°еҢәжҮҮи«ҮдјҡгҖҖйҖЈз¶ҡдјҒз”»
гҖҢж•ҷе®ӨпјҸеӨ§еӯҰгҒЁгҒ„гҒҶгғ•гӮЈгғјгғ«гғүвҖ•вҖ•ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®дҪ•гӮ’гҒ©гҒҶдјқгҒҲгӮӢгҒӢгҖҚ
гҖҖеәғгҒҸеёӮж°‘гҖҒзӨҫдјҡдёҖиҲ¬гҒ«гҒҹгҒ„гҒ—гҖҒж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ«гӮҲгӮӢд»•дәӢгҒ®жҲҗжһңгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҷәдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’е•ҸгҒҶгҒ•гҒ„гҒ«гҖҒеӨ§еӯҰгҒ®еӯҰз”ҹгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮиә«иҝ‘гҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮЁгғігӮ№гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеҪјгӮүгҒ«ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®дҪ•гӮ’гҒ©гҒҶдјқгҒҲгҒҹгӮүгҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еӯҰе•ҸгҒ®зӨҫдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж„Ҹзҫ©еҪ№еүІгӮ’гҒ©гҒҶзҷәдҝЎгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиӯ°и«–гҒ«гӮӮгӮҖгҒҷгҒігҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒЁгҒ„гҒҶеӯҰе•ҸгҒ®еӯҳеңЁж„Ҹзҫ©гӮ’зӨҫдјҡгҒ«зӨәгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒжң¬еӯҰе•Ҹй ҳеҹҹгҒ®д»ҠеҫҢгҒ®зҷәеұ•гҒ®еңЁгӮҠж–№гҒ«еӨ§гҒ„гҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒзҸҫеңЁгҒ®еӨ§еӯҰж•ҷиӮІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ еӯҰз”ҹгҒ«гӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖҒгҖҢйқўзҷҪгҒ„гҖҚжҺҲжҘӯгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҖҒгҒ©гҒҶе·ҘеӨ«гҒҷгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢпјҹпјҹж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҒ„гҒҫгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҺҲжҘӯгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮеҗ„еӨ§еӯҰгҒҜж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгӮ’гҒ©гҒҶдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гҖҒж•ҷе“ЎгҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжңҹеҫ…гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
гҖҖжң¬дјҒз”»гҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®жҺҲжҘӯгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶжғ…е ұгӮ’дә’гҒ„гҒ«дәӨжҸӣгҖҒе…ұжңүгҒ—гҖҒеҗ„дәәгҒҢгӮҲгӮҠиҮӘеҲҶгҒ®з ”究иғҢжҷҜгӮ’з”ҹгҒӢгҒ—гҒҹгҖҒгҒӢгҒӨеӯҰз”ҹгҒ«гӮӮ еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„пјҸеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„жҺҲжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶе·ҘеӨ«гӮ’з·ҙгӮҠгҒ гҒҷгҒ“гҒЁгӮ’иӘІйЎҢгҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒжҺҲжҘӯгҒ®еҚҳгҒӘгӮӢгғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖҒж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ«дҪ•гҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒеҗ„дәәгҒҢж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгӮ’гҒ©гҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«й–ўдҝӮгҒҷгӮӢи©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгӮ’е…ұжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒ„гҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдҪңжҘӯгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒӢгӮүжҢҒгҒЎеё°гҒЈгҒҹгғҮгғјгӮҝгҖҒдәәйЎһеӯҰзҡ„зҹҘгӮ’гҖҒж•ҷе®ӨпјҸеӨ§еӯҰгҒЁгҒ„гҒҶгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒ§гҒ©гҒҶе®ҹи·өгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ
第24жңҹж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰдјҡй–ўжқұең°еҢәжҮҮи«Үдјҡе№№дәӢ
зҹіз”°ж…ҺдёҖйғҺгҖҒжӨҺйҮҺиӢҘиҸңгҖҒеӯ«жҡҒеүӣгҖҒй«ҳйҮҺгҒ•гӮ„гҒӢгҖҒжқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺгҖҒжёЎйӮүжҡҒеӯҗ
жӢ…еҪ“зҗҶдәӢгҖҖ
дёүе°ҫиЈ•еӯҗ
пјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡ
гҖҢж•ҷе®ӨпјҸеӨ§еӯҰгҒЁгҒ„гҒҶгғ•гӮЈгғјгғ«гғүвҖ•вҖ•ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®дҪ•гӮ’гҒ©гҒҶдјқгҒҲгӮӢгҒӢгҖҚгҖҖ第дёҖеӣһгҖҖжҰӮи«–з·Ё
ж—ҘжҷӮгҖҖ2010е№ҙ11жңҲ6ж—ҘгҖҖгҖҖ13пјҡ30~17пјҡ30
е ҙжүҖгҖҖз«Ӣж•ҷеӨ§еӯҰжұ иўӢгӮӯгғЈгғігғ‘гӮ№гҖҖ12еҸ·йӨЁгҖҖ第дёҖгғ»з¬¬дәҢдјҡиӯ°е®ӨпјҲең°дёӢпј‘пјҰпјү
http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/campusmap/
гҖҗгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖ‘
и¶Јж—ЁиӘ¬жҳҺгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸңгҖҖ13пјҡ30пҪһ13пјҡ40
第дёҖйғЁгҖҖ13пјҡ40пҪһ15пјҡ10
зҹіз”°ж…ҺдёҖйғҺгҖҒж·ұз”°ж·іеӨӘйғҺгҖҒжӨҚжқ‘жё…еҠ гҖҒе°ҸиҘҝе…¬еӨ§
дј‘жҶ© 15пјҡ10пҪһ15пјҡ30
第дәҢйғЁ 15пјҡ30пҪһ17пјҡ00
йҲҙжңЁжҙӢе№ігҖҒгғўгғҸгғјгғҒгғ»гӮІгғ«гӮІгӮӨгҖҒз”°дёӯеӨ§д»ӢгҖҒй«ҳж©ӢзөөйҮҢйҰҷ
гғҮгӮЈгӮ№гӮ«гғғгӮ·гғ§гғі 17пјҡ00пҪһ17пјҡ30
в—ҸйҖЈзөЎе…Ҳв—Ҹ
жқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺпјҲз«Ӣж•ҷеӨ§еӯҰпјүkmatsumura[at]rikkyo.ac.jp
жӨҺйҮҺиӢҘиҸңпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖпјүwakana[at]aa.tufs.ac.jp
в—ҸдјҒз”»гҒёгҒ®гҒ”ж„ҸиҰӢгҖҒгҒ”иіӘе•ҸзӯүгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒёв—Ҹ
bunka.jinrui.kanto2010@gmail.com
第дәҢеӣһгҒҜгҖҒ12жңҲ18ж—Ҙй–ӢеӮ¬гҒ§гҒҷпјҒпјҒ
http://wakana-luo.aacore.jp/shiinoproject
null
гғ•гғ©гӮӨгғӨгғјгҒҜгҒ“гҒЎгӮүвҶ“
null
2010гҖҒ2011е№ҙеәҰгҒЁж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰдјҡгҒ®й–ўжқұең°еҢәжҮҮи«ҮдјҡгҒ®е№№дәӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәәйҒёгҒ—гҒҰгҖҒзҹіз”°ж…ҺдёҖйғҺгҖҒеӯ«жҡҒеүӣгҖҒй«ҳйҮҺгҒ•гӮ„гҒӢгҖҒжқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺгҖҒжёЎйӮүжҡҒеӯҗгҒ•гӮ“гӮүгӮ’гҒІгҒҚгҒ“гҒҝгҖҒ
дјҡеҗҲгӮ’гҒІгӮүгҒҚгҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢиӯ°и«–гҒ—гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдјҒз”»гӮ’гҒӢгӮ“гҒҢгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2010е№ҙеәҰпҪһгҖҖж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰдјҡй–ўжқұең°еҢәжҮҮи«ҮдјҡгҖҖйҖЈз¶ҡдјҒз”»
гҖҢж•ҷе®ӨпјҸеӨ§еӯҰгҒЁгҒ„гҒҶгғ•гӮЈгғјгғ«гғүвҖ•вҖ•ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®дҪ•гӮ’гҒ©гҒҶдјқгҒҲгӮӢгҒӢгҖҚ
гҖҖеәғгҒҸеёӮж°‘гҖҒзӨҫдјҡдёҖиҲ¬гҒ«гҒҹгҒ„гҒ—гҖҒж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ«гӮҲгӮӢд»•дәӢгҒ®жҲҗжһңгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҷәдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’е•ҸгҒҶгҒ•гҒ„гҒ«гҖҒеӨ§еӯҰгҒ®еӯҰз”ҹгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮиә«иҝ‘гҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮЁгғігӮ№гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеҪјгӮүгҒ«ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®дҪ•гӮ’гҒ©гҒҶдјқгҒҲгҒҹгӮүгҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еӯҰе•ҸгҒ®зӨҫдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж„Ҹзҫ©еҪ№еүІгӮ’гҒ©гҒҶзҷәдҝЎгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиӯ°и«–гҒ«гӮӮгӮҖгҒҷгҒігҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒЁгҒ„гҒҶеӯҰе•ҸгҒ®еӯҳеңЁж„Ҹзҫ©гӮ’зӨҫдјҡгҒ«зӨәгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒжң¬еӯҰе•Ҹй ҳеҹҹгҒ®д»ҠеҫҢгҒ®зҷәеұ•гҒ®еңЁгӮҠж–№гҒ«еӨ§гҒ„гҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒзҸҫеңЁгҒ®еӨ§еӯҰж•ҷиӮІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ еӯҰз”ҹгҒ«гӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖҒгҖҢйқўзҷҪгҒ„гҖҚжҺҲжҘӯгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҖҒгҒ©гҒҶе·ҘеӨ«гҒҷгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢпјҹпјҹж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҒ„гҒҫгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҺҲжҘӯгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮеҗ„еӨ§еӯҰгҒҜж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгӮ’гҒ©гҒҶдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гҖҒж•ҷе“ЎгҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжңҹеҫ…гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
гҖҖжң¬дјҒз”»гҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®жҺҲжҘӯгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶжғ…е ұгӮ’дә’гҒ„гҒ«дәӨжҸӣгҖҒе…ұжңүгҒ—гҖҒеҗ„дәәгҒҢгӮҲгӮҠиҮӘеҲҶгҒ®з ”究иғҢжҷҜгӮ’з”ҹгҒӢгҒ—гҒҹгҖҒгҒӢгҒӨеӯҰз”ҹгҒ«гӮӮ еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„пјҸеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„жҺҲжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶе·ҘеӨ«гӮ’з·ҙгӮҠгҒ гҒҷгҒ“гҒЁгӮ’иӘІйЎҢгҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒжҺҲжҘӯгҒ®еҚҳгҒӘгӮӢгғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖҒж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ«дҪ•гҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒеҗ„дәәгҒҢж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгӮ’гҒ©гҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«й–ўдҝӮгҒҷгӮӢи©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгӮ’е…ұжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒ„гҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдҪңжҘӯгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒӢгӮүжҢҒгҒЎеё°гҒЈгҒҹгғҮгғјгӮҝгҖҒдәәйЎһеӯҰзҡ„зҹҘгӮ’гҖҒж•ҷе®ӨпјҸеӨ§еӯҰгҒЁгҒ„гҒҶгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгҒ§гҒ©гҒҶе®ҹи·өгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ
第24жңҹж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰдјҡй–ўжқұең°еҢәжҮҮи«Үдјҡе№№дәӢ
зҹіз”°ж…ҺдёҖйғҺгҖҒжӨҺйҮҺиӢҘиҸңгҖҒеӯ«жҡҒеүӣгҖҒй«ҳйҮҺгҒ•гӮ„гҒӢгҖҒжқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺгҖҒжёЎйӮүжҡҒеӯҗ
жӢ…еҪ“зҗҶдәӢгҖҖ
дёүе°ҫиЈ•еӯҗ
пјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡпјҡ
гҖҢж•ҷе®ӨпјҸеӨ§еӯҰгҒЁгҒ„гҒҶгғ•гӮЈгғјгғ«гғүвҖ•вҖ•ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰгҒ®дҪ•гӮ’гҒ©гҒҶдјқгҒҲгӮӢгҒӢгҖҚгҖҖ第дёҖеӣһгҖҖжҰӮи«–з·Ё
ж—ҘжҷӮгҖҖ2010е№ҙ11жңҲ6ж—ҘгҖҖгҖҖ13пјҡ30~17пјҡ30
е ҙжүҖгҖҖз«Ӣж•ҷеӨ§еӯҰжұ иўӢгӮӯгғЈгғігғ‘гӮ№гҖҖ12еҸ·йӨЁгҖҖ第дёҖгғ»з¬¬дәҢдјҡиӯ°е®ӨпјҲең°дёӢпј‘пјҰпјү
http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/campusmap/
гҖҗгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖ‘
и¶Јж—ЁиӘ¬жҳҺгҖҖжӨҺйҮҺиӢҘиҸңгҖҖ13пјҡ30пҪһ13пјҡ40
第дёҖйғЁгҖҖ13пјҡ40пҪһ15пјҡ10
зҹіз”°ж…ҺдёҖйғҺгҖҒж·ұз”°ж·іеӨӘйғҺгҖҒжӨҚжқ‘жё…еҠ гҖҒе°ҸиҘҝе…¬еӨ§
дј‘жҶ© 15пјҡ10пҪһ15пјҡ30
第дәҢйғЁ 15пјҡ30пҪһ17пјҡ00
йҲҙжңЁжҙӢе№ігҖҒгғўгғҸгғјгғҒгғ»гӮІгғ«гӮІгӮӨгҖҒз”°дёӯеӨ§д»ӢгҖҒй«ҳж©ӢзөөйҮҢйҰҷ
гғҮгӮЈгӮ№гӮ«гғғгӮ·гғ§гғі 17пјҡ00пҪһ17пјҡ30
в—ҸйҖЈзөЎе…Ҳв—Ҹ
жқҫжқ‘еңӯдёҖйғҺпјҲз«Ӣж•ҷеӨ§еӯҰпјүkmatsumura[at]rikkyo.ac.jp
жӨҺйҮҺиӢҘиҸңпјҲжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰгӮўгӮёгӮўгғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«иЁҖиӘһж–ҮеҢ–з ”з©¶жүҖпјүwakana[at]aa.tufs.ac.jp
в—ҸдјҒз”»гҒёгҒ®гҒ”ж„ҸиҰӢгҖҒгҒ”иіӘе•ҸзӯүгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒёв—Ҹ
bunka.jinrui.kanto2010@gmail.com
第дәҢеӣһгҒҜгҖҒ12жңҲ18ж—Ҙй–ӢеӮ¬гҒ§гҒҷпјҒпјҒ
http://wakana-luo.aacore.jp/shiinoproject
null
Posted by: shiino 2010/10/24 03:03:49